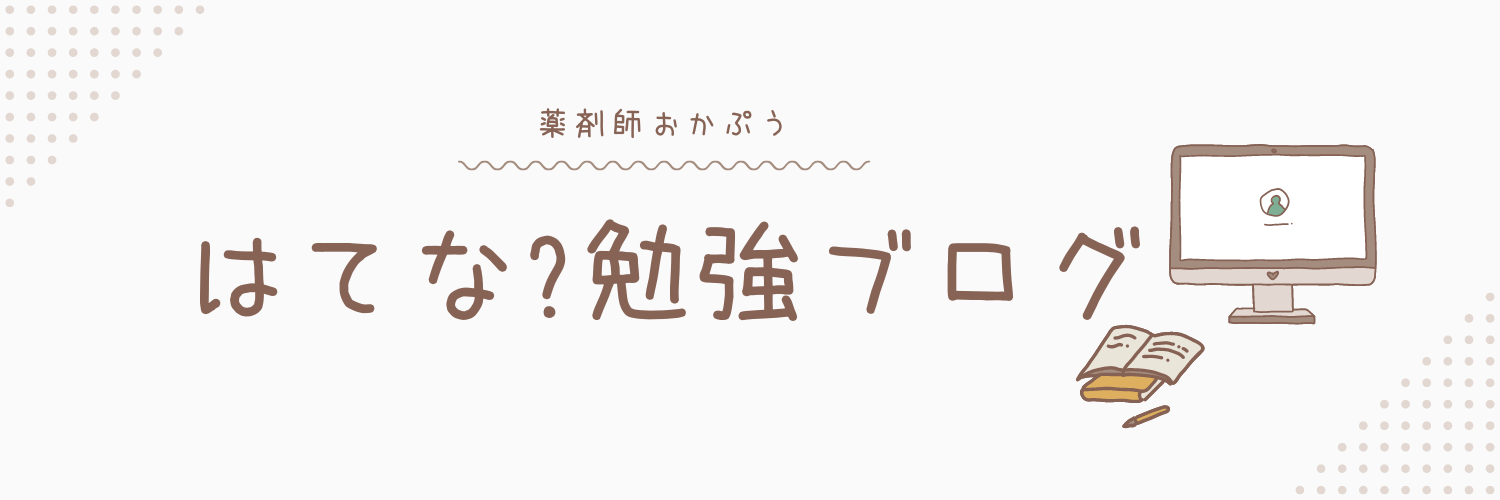最近、「高校生の子が心療内科や精神科に通って向精神薬や抗不安薬を飲んでいる」という話を耳にする機会が増えてきました。社会的にメンタルケアへの理解が広がったのは良いことやけど、一方で 「薬ありき」 の対応には少し違和感を覚える人も多いんちゃうかなと思います。
僕自身も「薬ってあくまで対症療法であって、根本治療にはならんのちゃう?」と感じています。
実際のエピソード
実はこのテーマを考えるきっかけになったのは、身近な家族の経験です。
甥っ子がメンタル面で薬を服用しているのですが、情緒が不安定になりやすく、学校に行きづらくなることもあります。
姉の話によると、以前は サバ缶を食べたり、祖母が作った自家製味噌の味噌汁を飲んでいた時期は調子が良かった そうです。サバにはオメガ3脂肪酸が豊富で、味噌は発酵食品として腸内環境を整える働きがあり、どちらも心の安定に関わるとされる食品です。
ところが最近は、甥っ子自身から「サバ缶が食べたい」「味噌汁が欲しい」と言うことが減り、自然と食卓からそれらが消えてしまった。もしかするとこの小さな変化が、情緒の揺れとリンクしているのかもしれません。
これは単なる栄養学の話だけやなく、家庭の中で安心できる「食の習慣」が心の支えになる という実例でもあると感じました。薬で症状を抑えるのも大事ですが、こうした身近な食材や食卓の雰囲気が持つ力も、見過ごせない要素だと思います。
向精神薬・抗不安薬の役割とリスク
- 薬はあくまで 症状を一時的に和らげる補助 的な存在。
- 特に抗不安薬(ベンゾジアゼピン系)は依存や離脱症状のリスクもある。
- 長期服用は脳の発達に未知の影響を及ぼす可能性があり、若年層では注意が必要。
もちろん「薬で救われる命」もあります。ただし、それだけで根本的な改善につながるかと言えば、疑問が残ります。
食生活とメンタルの関係(エビデンスあり)
意外と見落とされがちなんが 毎日の食生活。ここが乱れてると、気分の波や不安感に直結することが、研究でも示されています。
- 食事パターンとメンタル
- 地中海食(魚・野菜・豆・全粒穀物中心)をとる人は、うつ病リスクが低いという報告が多数。
- 一方、ジャンクフードや超加工食品を多く摂る人は、うつ病や不安症状のリスクが上昇。
- 腸内環境(腸脳相関)
- 腸内細菌のバランスが乱れると、不安や抑うつが悪化しやすい。
- 発酵食品や食物繊維の摂取は腸内環境を整え、気分の改善に寄与する可能性が報告されている。
- 必須栄養素不足
- 鉄 → 集中力低下や抑うつ気分
- ビタミンB群 → 神経伝達物質の合成に不可欠
- ω3脂肪酸 → 不足すると炎症が増えて気分障害のリスク上昇
こうしたエビデンスは「薬食同源」の考え方を裏づけるものでもあります。
薬の前にできること
薬を飲む前に、こんなことから見直してみるのがおすすめです。
- 睡眠リズムを整える(夜更かしスマホを控える)
- タンパク質をしっかり摂る(魚・卵・豆など)
- 発酵食品や食物繊維で腸内環境を改善
- 間食やジャンクを控え、砂糖を摂りすぎない
- こまめな水分補給
これだけでも、気分の安定や集中力の改善を感じる子は少なくありません。
自然な食材を「一品足す」発想
薬やサプリに頼る前に、自然な食材を普段の食事にちょっと足すだけでも効果は期待できます。
- 発酵食品:納豆、ヨーグルト、味噌汁、キムチ
- 魚:サバ、イワシ、サケ(オメガ3脂肪酸)
- 野菜:緑黄色野菜(抗酸化物質・ビタミン)
- ナッツ類:クルミ、アーモンド(良質な脂質+ミネラル)
- 果物:バナナ(セロトニンの材料になるトリプトファンを含む)
特別なことをせんでも、「毎日の食卓に一品加える」くらいの小さな工夫で、体への負担なくじわじわと心身を整えていけます。
まとめ
向精神薬や抗不安薬は決して悪ではなく、必要な場面で大きな助けになります。
ただし、若年層のメンタル不調においては 薬だけに頼るんやなくて「食・睡眠・生活習慣」こそ根本改善のカギ。
「薬食同源」という言葉があるように、日々の食事が心と体を作ります。
高校生のメンタルケアを考えるなら、まずは食卓から見直していきたいですね。
参考文献
- Sanchez-Villegas A, et al. Mediterranean dietary pattern and depression. Public Health Nutr. 2016.
- Lassale C, et al. Healthy dietary indices and risk of depressive outcomes. Mol Psychiatry. 2019.
- Silva H, et al. Mediterranean Diet and Mental Health in Adolescents. Nutrients. 2023.
- O’Neil A, et al. Relationship between diet and mental health in children and adolescents. Am J Public Health. 2014.
- Mayer EA, et al. Gut/brain axis and the microbiota. J Clin Invest. 2015.
- Sarkar A, et al. Psychobiotics and the manipulation of bacteria–gut–brain signals. Trends Neurosci. 2016.
参考文献リスト
① 地中海食と若年層のメンタル
- 地中海食は、魚・野菜・豆・全粒穀物を中心とする食事で、若年層のうつリスクを低減する可能性が示されています PMCPubMed。
- スペインの研究では、メディタレニアン食の摂取が多い高校〜青年で、行動問題や衝動性が少なく、プロソーシャル行動が多い傾向が見られました MDPI。
② 食事パターンと精神症状
- オーストラリアの研究では、健康的な食事をする若年層は、抑うつ・不安症状が少ない傾向がある一方、ジャンクフード中心の子はそうした症状が多いという結果が報告されています BioMed Central。
- カナダの大規模コホートでは、砂糖入り飲料の摂取はうつ・不安が悪化する一方、果物・野菜の摂取は心理的幸福度の向上と関連していました CDC。
③ 腸脳相関(Gut-Brain Axis)と発酵食品・プロバイオティクス
- 腸と脳は相互作用しており、腸内環境の乱れが不安やうつに関与しているという研究もあります PubMedウィキペディア。
- 発酵食品に含まれるプロバイオティクス(例:Lactobacillusなど)が、神経伝達物質の生成や炎症の抑制、ストレス反応の調整などを通じてメンタルを整える可能性があります SpringerLinkFrontiersウィキペディア。
- 実際、発酵食品+食物繊維を日常的に摂ることで、ストレスが軽減されたという報告もあるで World Economic Forum。
④ 若年層への食事介入の効果(RCT/レビュー)
13〜40歳を対象にした食事介入のRCTレビューでは、数例でうつ症状やQOL(生活の質)の改善が確認された一方、エビデンスの一貫性はまだ弱いという結果でした MDPI。