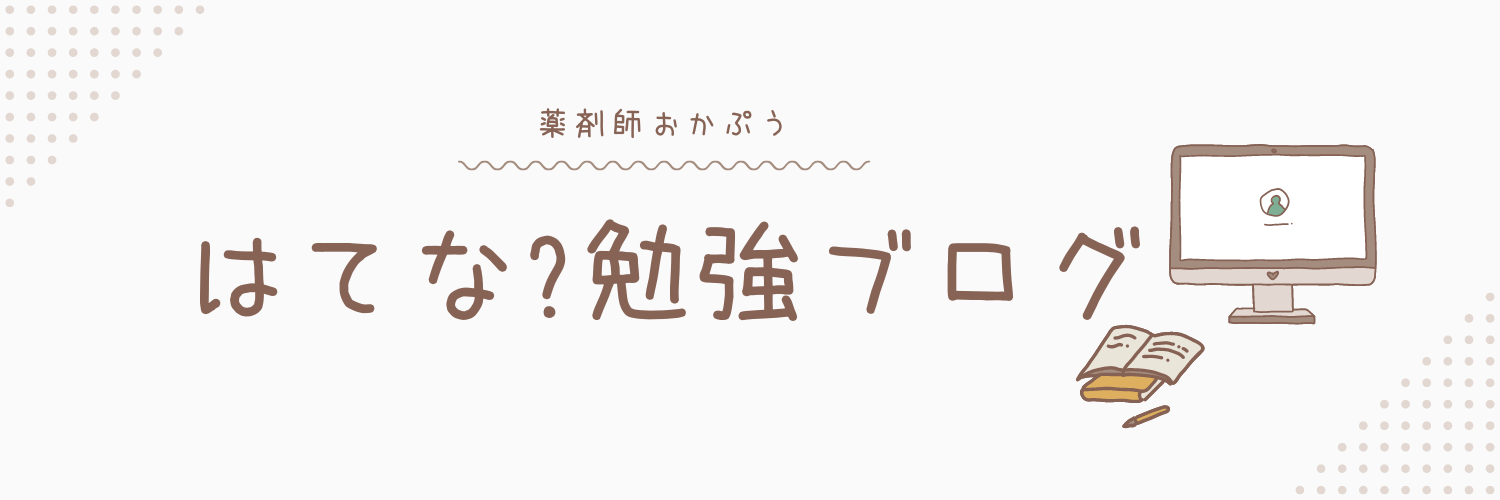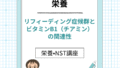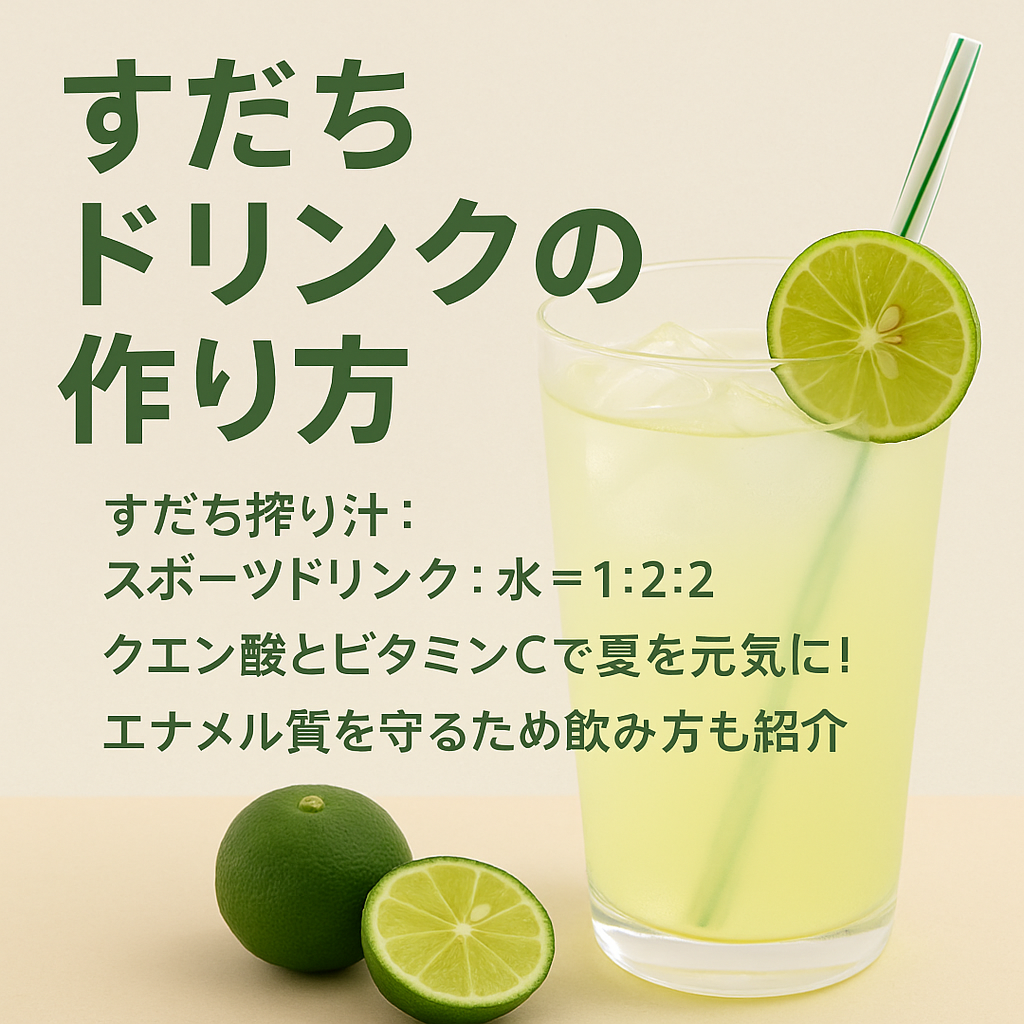病院で処方されることの多い亜鉛含有製剤。
味覚障害や褥瘡治療などで長期服用されることがありますが、注意点として**「銅欠乏性貧血」**が知られています。今回はその理由と予防策について解説します。
亜鉛と銅の関係性
亜鉛と銅はどちらも必須ミネラルで、小腸での吸収経路が共通しています。
特に「メタロチオネイン」というタンパク質が関わっており、亜鉛を多く摂るとこのタンパク質が増加します。
実はこのメタロチオネインは銅をより強く捕まえる性質があるため、銅が腸管細胞に閉じ込められて体外に排出されてしまうのです。
その結果、体内に取り込まれる銅が不足していきます。
銅欠乏で起こる症状
銅が不足すると、銅を必要とする酵素が働かなくなり、造血がうまくいかなくなります。
代表的な症状は次の通りです。
- 貧血(銅欠乏性貧血)
- 白血球減少
- 神経障害(しびれ、ふらつき、重症では脊髄変性)
- 汎血球減少症(赤血球・白血球・血小板すべてが低下)
予防するためのポイント
亜鉛製剤が必要な患者さんでも、次のような対策で銅欠乏を防ぐことが可能です。
- 定期的な採血チェック
- 亜鉛・銅の血清値を3か月ごとに確認
- 神経症状や血球減少が出たら要注意
- 投与量・期間の適正化
- 必要最小限の量にとどめる
- 亜鉛が過剰(例:250µg/dL以上)なら減量・中止を検討
- 銅補充の工夫
- 食事:ココアパウダー、ナッツ、レバー、甲殻類など
- 医療現場:微量元素製剤を併用する場合も
栄養教育でのキーワード
- 亜鉛 → 「牡蠣」
- 銅 → 「ココアパウダー」
患者さんやスタッフ教育のときに、このイメージで説明すると覚えやすいです。
まとめ
亜鉛製剤は有用ですが、長期服用=銅欠乏リスクを常に意識する必要があります。
定期的なモニタリングと食事・補充の工夫で、安全に継続できるようにしましょう。