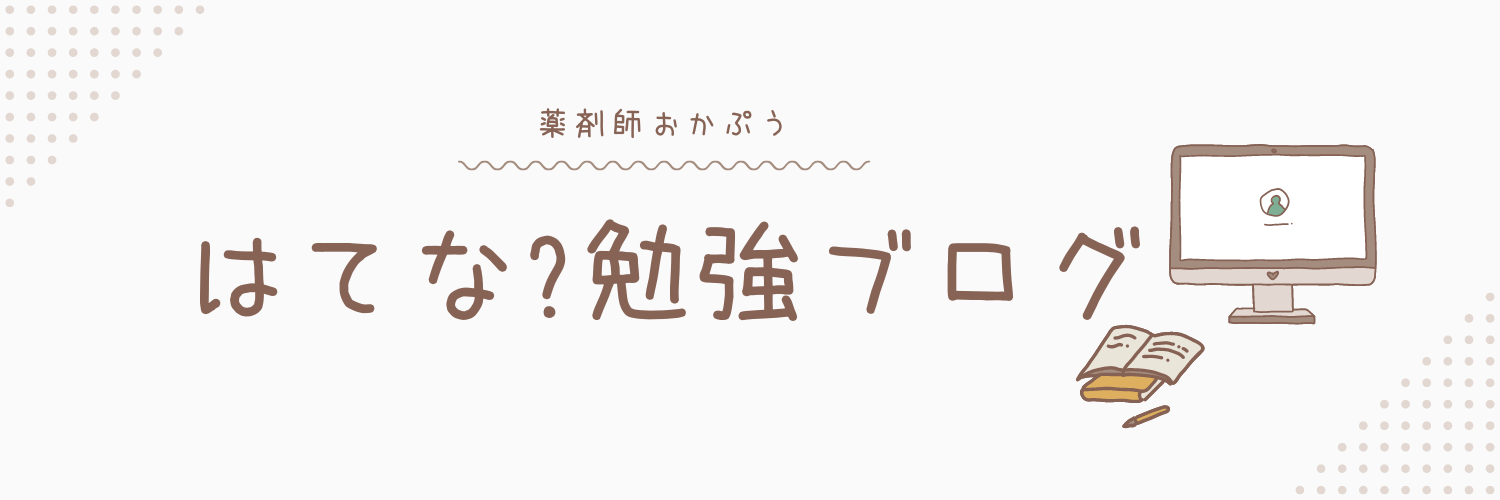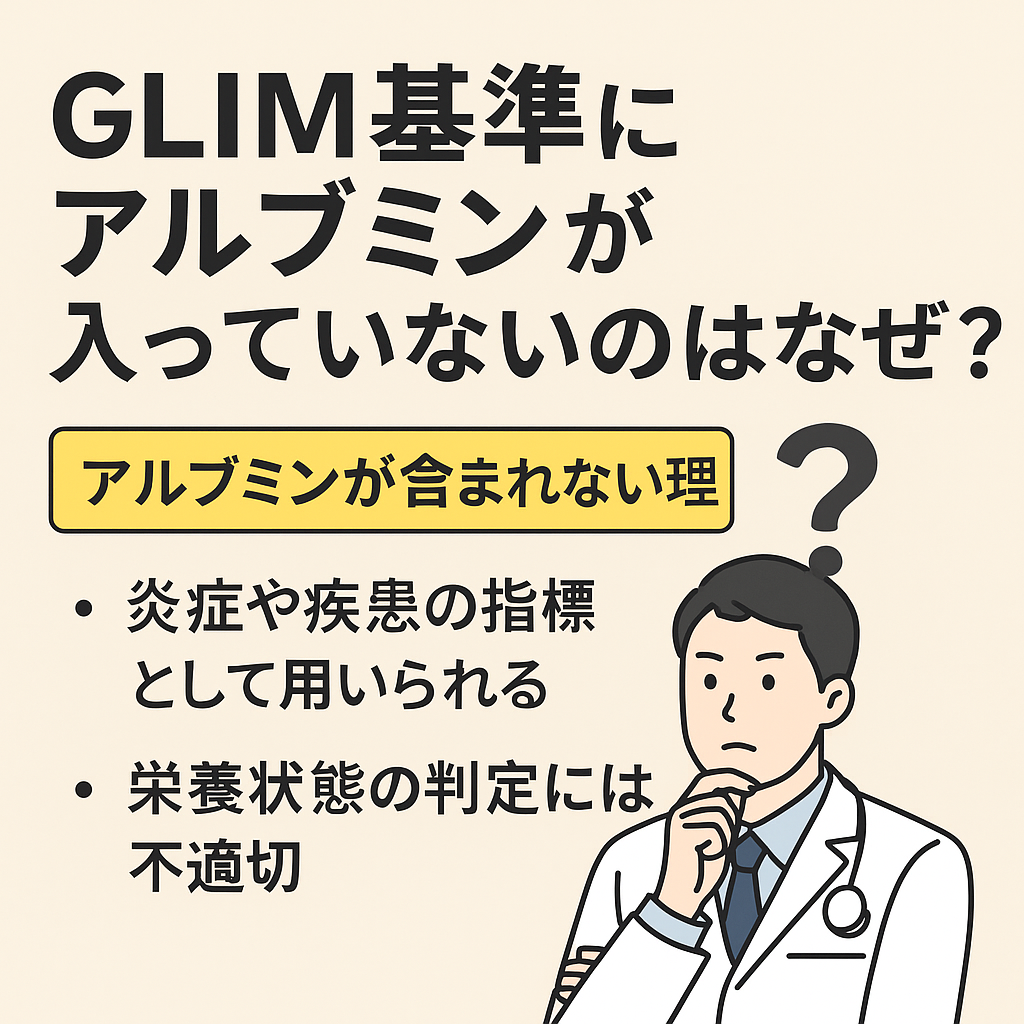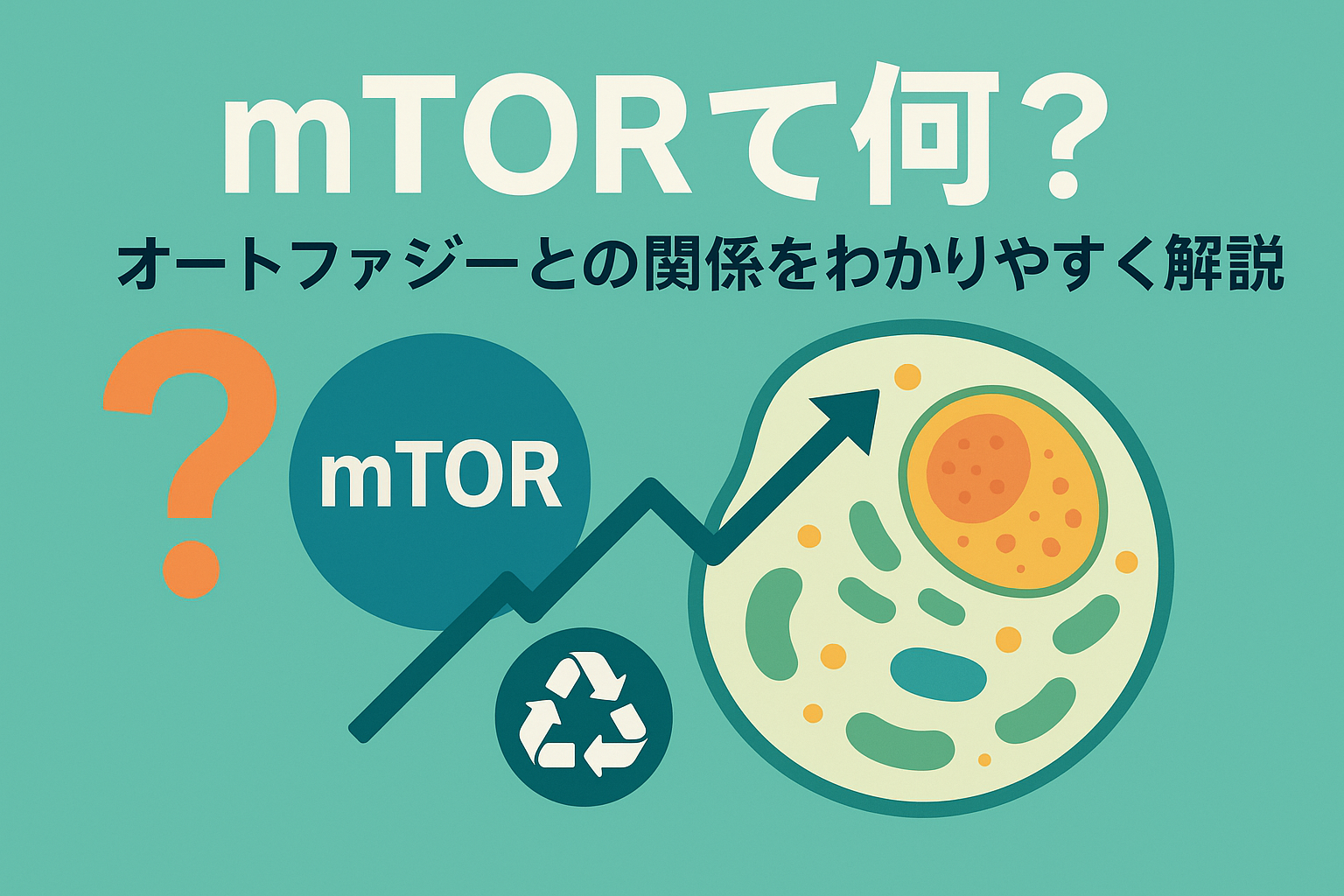栄養評価の国際基準であるGLIM基準(Global Leadership Initiative on Malnutrition)には、血清アルブミン値が含まれていません。
「低アルブミン=低栄養」というイメージを持っていた人にとっては意外かもしれません。では、なぜ外されたのでしょうか。
アルブミンは“栄養指標”ではない
これまでアルブミンは「栄養状態を映す数値」として使われてきました。
しかし、近年の研究ではアルブミン値は体内のたんぱく質量や筋肉量、栄養状態とは強く結びついていないことが示されています。
つまり「アルブミンが低い=栄養不良」とは言えないのです。
炎症・疾患の影響を強く受ける
アルブミン値は、感染症や手術後などの炎症状態、あるいは肝機能・腎機能といった臓器の状態に大きく左右されます。
このため、**栄養というより“炎症や疾患のマーカー”**としての意味合いが強いと考えられるようになりました。
ASPEN(米国静脈経腸栄養学会)などの国際的な基準でも、「アルブミンは栄養指標ではなく炎症指標である」と明確に述べられています。
GLIM基準が重視する評価
GLIM基準では、実際に患者の身体に起きている変化を見て診断します。
- 体重減少の有無
- 食事摂取量の低下
- 筋肉量の減少
- 皮下脂肪の減少
- 握力の低下
さらに、MUSTやMNA®-SFなど科学的に妥当性が認められたスクリーニングツールの利用が推奨されています。
これにより、血液検査を行わなくても、ベッドサイドで患者の状態を把握できる仕組みになっています。
まとめ
アルブミンは予後や炎症を示す重要な数値ですが、栄養不良の診断に用いるべきではないというのが国際的な共通認識です。
GLIM基準は「身体的・機能的な変化」を診ることに重きを置き、より臨床的に役立つ診断を目指しています。
若手医療職にとって大切なのは、「アルブミン低値=低栄養」と短絡的に結びつけないこと。
患者さんの全体像を評価する力が求められています。
参考:日本栄養治療学会-GLIM基準

GLIM基準に関連する書籍
 | これですぐ始められる!GLIMで低栄養診断 徹底解説 [ 吉⽥貞夫 ] 価格:2970円 |
 | Nutrition Care 第18巻9号(2025−9) GLIM基準による低栄養診断の実際 価格:2200円 |