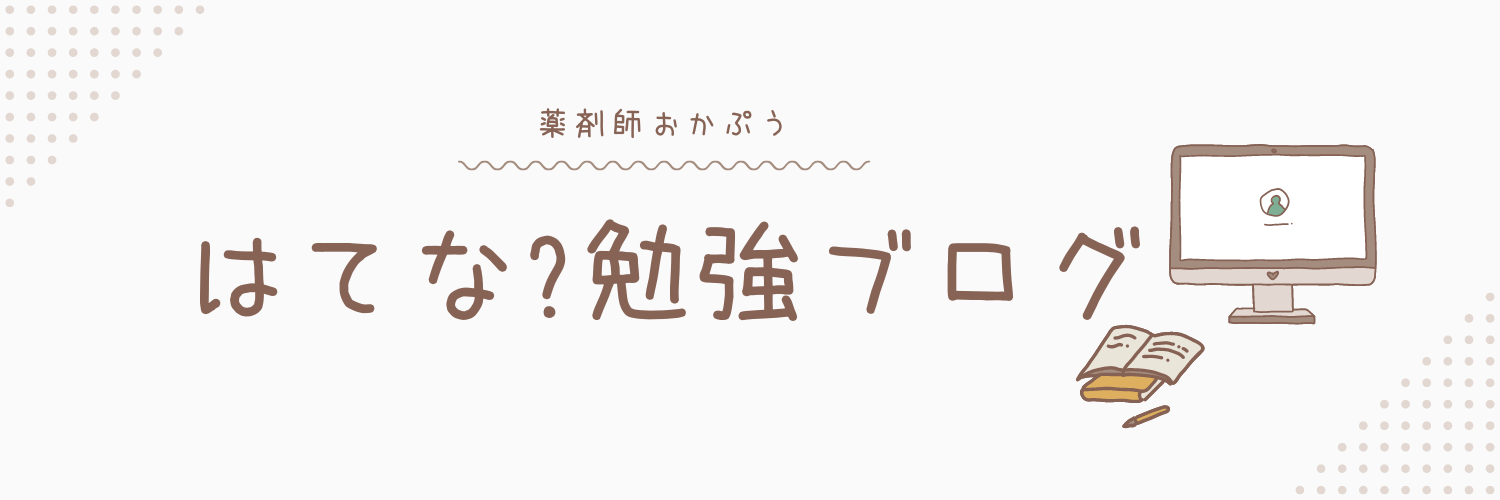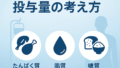はじめに
入院や加齢、慢性疾患などによって「低栄養」のリスクは誰にでも起こり得ます。低栄養は免疫力や治療効果の低下につながるため、医療・介護現場では早期に発見し、適切に対応することが欠かせません。
その第一歩が 「栄養スクリーニング」 であり、国際的な診断基準として注目されているのが 「GLIM基準」 です。この記事では、両者の流れと活用方法をわかりやすく解説します。
栄養スクリーニングとは?
栄養スクリーニングは、すべての患者さんを対象に短時間で「低栄養リスクの有無」を判定する一次評価です。
信頼性の高い検証済みツールを用いることで、見逃しを防ぎ、必要な人に早期介入できます。
代表的なツールには以下があります:
- MNA®-SF(高齢者向け):食事量・体重減少・BMIなど6項目
- MUST(成人向け):BMI・体重減少・急性疾患の3項目
- NRS2002(入院患者向け):疾患の重症度や年齢を加味
- MST(病院・施設向け):体重減少と食欲低下の2問のみ
- SGA(総合評価):問診と身体所見を組み合わせた判定
仮の栄養スクリーニング表の画像
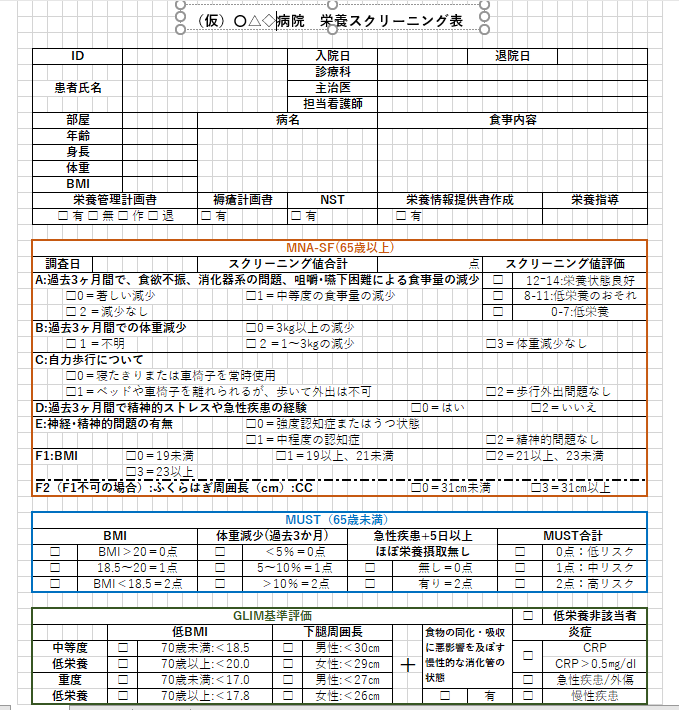
GLIM基準とは?
GLIM(Global Leadership Initiative on Malnutrition)基準は、国際的な栄養学会が合意した「低栄養の診断基準」です。大きく3つのステップで構成されています。
- スクリーニング
MUSTやMNA-SFなどを使って低栄養リスクを判定 - 診断(2カテゴリーから各1項目以上)
- 表現型基準(フェノタイプ)
- 意図しない体重減少
- 低BMI
- 筋肉量の減少
- 病因基準(エチオロジー)
- 食事摂取量の減少または消化吸収の低下
- 疾患負荷や炎症の存在
→ 双方から1つずつ該当すると「低栄養」と診断されます。
- 重症度判定
体重減少率やBMIの程度をもとに「中等度」または「重度」に分類
GLIM基準のメリット
- 国際的に統一された診断基準であること
- 疾患関連の低栄養(炎症・吸収不良など)も評価できる
- スクリーニングから診断、重症度判定まで一貫して行える
つまり、栄養スクリーニングで拾い上げ → GLIM基準で診断・重症度判定 → 適切な介入へ という流れが確立されます。
まとめ
低栄養は患者さんの予後を左右する大きな要因です。
- 栄養スクリーニングでまずリスクをチェック
- GLIM基準で客観的かつ国際標準の診断を実施
- 早期に介入することで治療効果やQOLを高める
医療職だけでなく、介護や地域包括ケアの現場でも活用できる知識です。日常のケアの中で「食べられているか」「体重が減っていないか」を意識し、早めの対応につなげましょう。
 | Nutrition Care 第18巻9号(2025−9) GLIM基準による低栄養診断の実際 価格:2200円 |
 | これですぐ始められる!GLIMで低栄養診断 徹底解説 [ 吉⽥貞夫 ] 価格:2970円 |