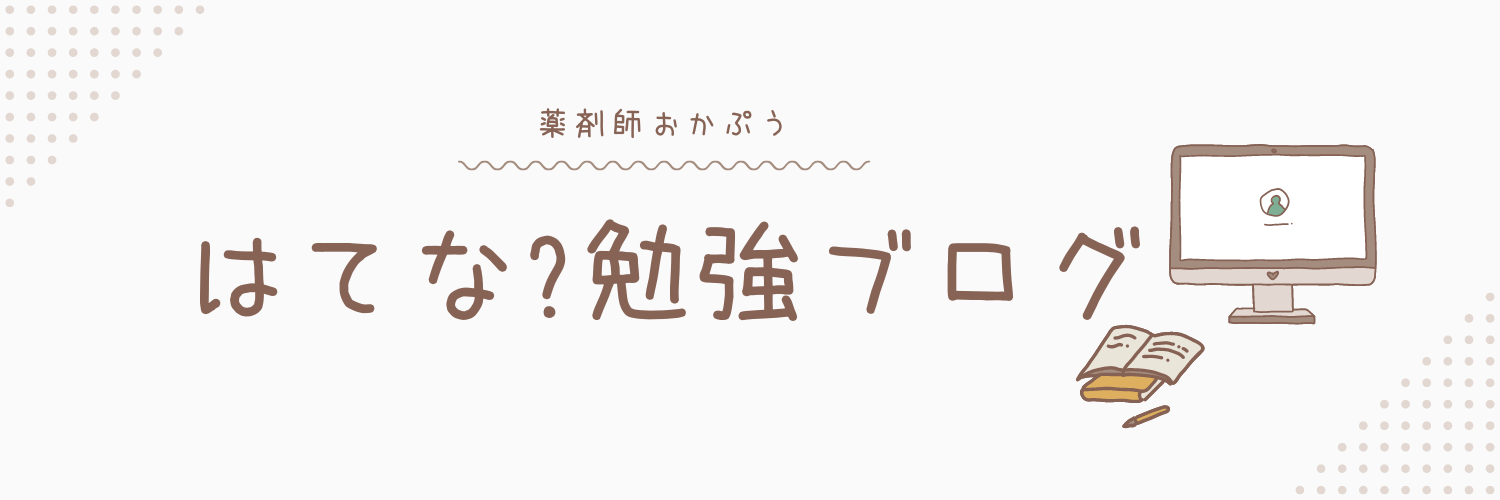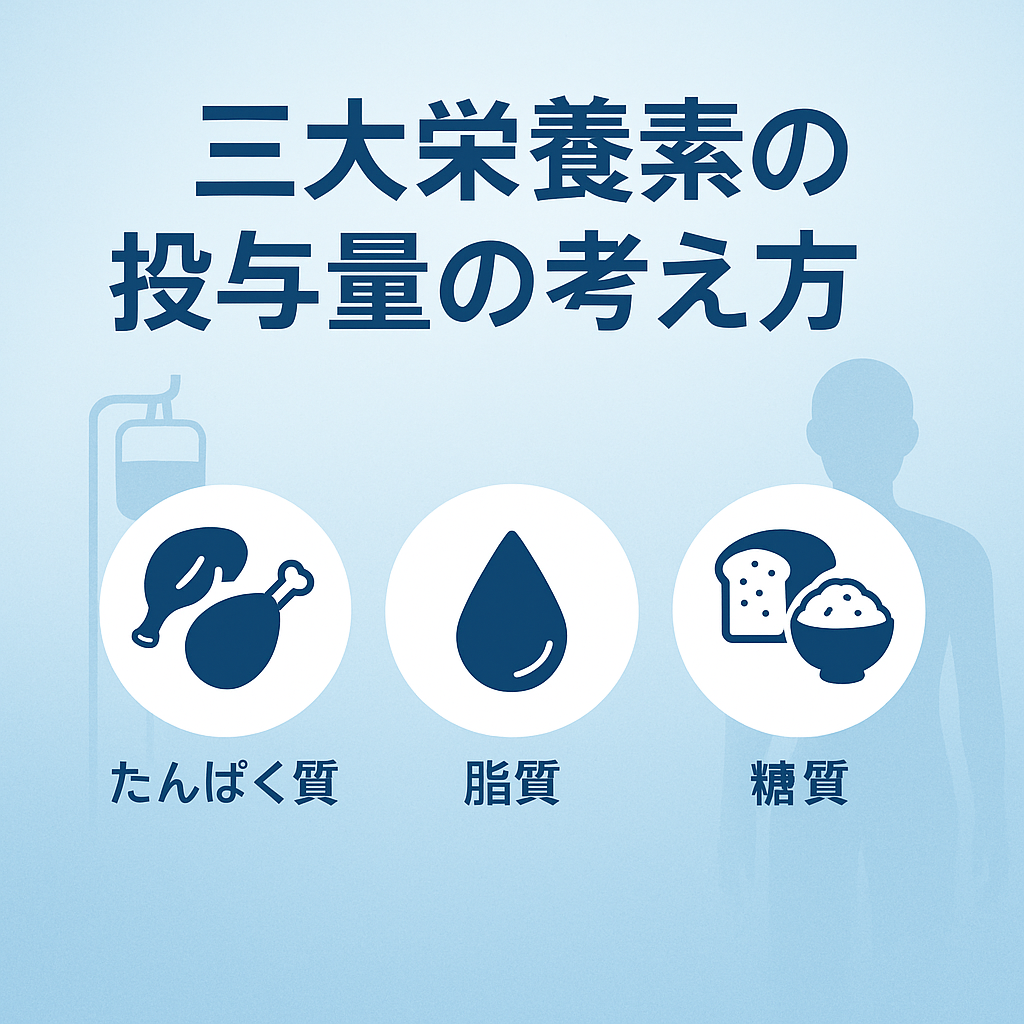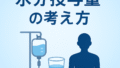導入文
栄養管理を行う上で欠かせないのが「エネルギー量の設定」や「栄養素バランス」の調整です。特に入院患者や静脈・経腸栄養を受ける患者さんでは、三大栄養素(たんぱく質・脂質・糖質)の配分を誤ると、十分に栄養が利用されず、かえって合併症を引き起こすこともあります。
そこで今回は、臨床現場でよく使うたんぱく質・脂質・糖質の投与量の決定方法について整理しました。これから学ぶ若手医療従事者の方や復習したい方に役立つ内容になっています。
① たんぱく質投与量
- 基準量:体重あたり0.8~1.0g/kg/日
- 病態ごとの調整例
- 外傷・手術・熱傷・褥瘡:必要量↑
- 保存期腎不全:0.6~0.8g/kg/日
- 血液透析:1.0~1.2g/kg/日
- 腹膜透析:1.1~1.3g/kg/日
- 肝硬変:1.0~1.3g/kg/日
- 肝性脳症(高アンモニア血症):0.5g/kg/日程度+BCAA製剤
NPC/N比
- 一般:150前後
- 侵襲時:100前後
- 腎不全:300以上
👉 NPC/N比を意識することで、投与したたんぱく質が効率よく体蛋白合成に利用されるかを評価できます。
② 脂質投与量
- 経腸栄養:総エネルギーの20~40%
- 静脈栄養:脂肪乳剤を併用
- 投与速度:0.1g/kg/時以下
- 1日投与量:1.0g/kg以上は避ける
- 一般的な目安:0.5~1.0g/kg/日(20~50g程度)
ポイント
- 1g=9kcalと高効率なエネルギー源
- COPDやARDSでは、炭水化物より脂質を優先 → 二酸化炭素産生を抑制できる
- 投与時はn-3系/n-6系脂肪酸のバランスにも注意
③ 糖質投与量
- 基準:総エネルギーの50~60%
- 静脈栄養:
- グルコース投与速度は 5mg/kg/分以下
- 侵襲時は 4mg/kg/分以下
注意点
- 感染症・侵襲時はインスリン抵抗性が亢進 → 高血糖リスク増大
- 高血糖は創傷治癒遅延・感染合併の原因になるため、血糖管理が重要
栄養素投与量の計算の流れ
- 蛋白質(アミノ酸)投与量
体重(kg) × ストレスファクター - 脂肪投与量
0.5~1.0g/kg(または総エネルギーの20~40%) - 糖質投与量
総エネルギー − 蛋白質由来エネルギー − 脂質由来エネルギー
👉 この順番で計算すると、過不足なくバランスよく投与できます。
まとめ
- たんぱく質:0.8~1.0g/kg/日を基準に病態で調整
- 脂質:総エネルギーの20~40%、投与速度制限に注意
- 糖質:総エネルギーの50~60%、侵襲時は耐糖能に注意
- NPC/N比:蛋白質の利用効率を評価する大切な指標
三大栄養素の配分は、単にエネルギーを満たすだけでなく、病態や合併症のリスクを考慮しながら調整することが重要です。日常の栄養管理のなかで、ぜひ意識してみてください。