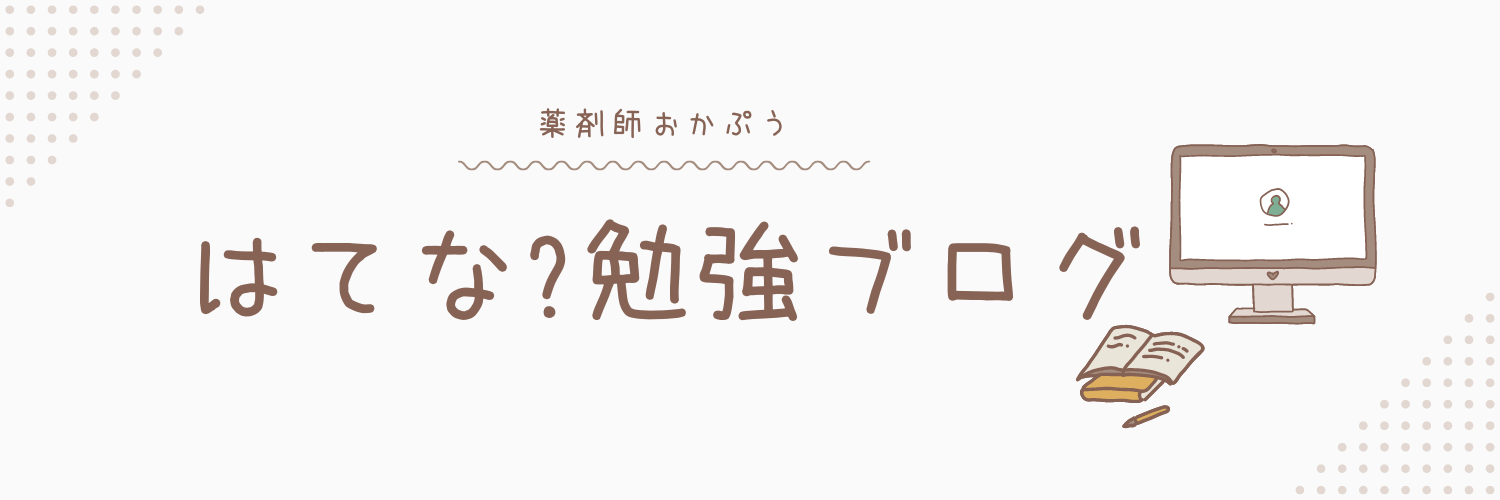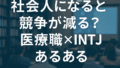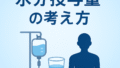こんにちは。病院で働いていると、静脈栄養や経腸栄養の処方に関わることが増えてきますよね。
「この患者さんにどれくらいカロリーを入れればいいの?」という疑問、若手の看護師さんや薬剤師さんなら一度は感じたことがあると思います。
今回は、エネルギー必要量(Energy Requirement) の基本的な考え方を整理してみます。
なぜ「エネルギー必要量」が大事なのか?
- 少なすぎる → 栄養障害や免疫低下につながり、創傷治癒も遅れる
- 多すぎる → overfeeding(過剰栄養)となり、高血糖・脂肪肝・呼吸不全などの合併症を引き起こす
つまり「適切なエネルギー量を見極めること」が、栄養管理のスタート地点です。
エネルギー必要量の求め方
エネルギー必要量は、以下の3つの方法で求められます。
① 間接カロリメトリー
呼気ガスから安静時エネルギー消費量を測定する方法。最も正確ですが、機器が必要でルーチンには難しいのが現状です。
② 予測式を用いる方法(Harris-Benedict式)
- 年齢・性別・身長・体重から「基礎エネルギー消費量(BEE)」を算出
男性:66.47+13.75×体重+5.0×身長-6.75×年齢
女性:655.1+9.56×W+1.85×身長-4.68×年齢
- さらに 活動係数(AF) と 傷害係数(SF) を掛け合わせて調整
例)エネルギー必要量 = BEE × AF × SF
③ 簡易式(25~30 kcal/kg)
「とりあえずの目安」を出したいときに便利。
特に高齢者や急性期は 25 kcal/kg で開始し、患者の反応を見て調整するのが安全です。
活動係数(AF)と傷害係数(SF)の目安
- AF(Activity Factor)
- 寝たきり覚醒:1.1
- ベッド上安静:1.2
- ベッド外活動あり:1.3~1.4
- SF(Stress Factor)
- 手術:1.1~1.8(侵襲度により調整)
- 敗血症・外傷:1.2~1.3
- 発熱:1℃ごとに約1.1倍
ケーススタディでイメージ!
ケース①:60歳男性(体重60kg、敗血症、中等度ストレス、ベッド上安静)
- BEE=1311 kcal
- AF=1.2、SF=1.3
- 必要量=1311 × 1.2 × 1.3 ≒ 2045 kcal/day
→ 簡易式(25~30 kcal/kg=1500~1800 kcal)よりも高め。重症例では予測式を使った方が現実に近い。
ケース②:75歳女性(体重40kg、寝たきり覚醒)
- BEE=964 kcal
- AF=1.1、SF=1.0
- 必要量=964 × 1.1 ≒ 1060 kcal/day
- 簡易式=1000 kcal
→ 高齢・低体重なので、25 kcal/kgで始めて安全に進めるのがポイント。
ケース③:50歳男性(肥満、体重90kg、骨折後リハビリ)
- 標準体重(IBW)=63.6kg
- 簡易式:25~30 kcal × IBW ≒ 1590~1900 kcal/day
→ 肥満患者は実体重で計算すると過大評価になりがち。IBWを使うのが安全。
実務で意識すべきポイント
- まずは25 kcal/kgで開始 → 評価しながら調整
- 重症例では予測式を活用して精度を上げる
- 肥満は標準体重、やせは健常時体重を使用
- 推定値にとらわれすぎず、バイタルや臨床経過を見ながら調整
まとめ
若手のうちは「式が難しそう」「計算がややこしい」と感じるかもしれません。
でも大事なのは、「患者さんにエネルギーを入れすぎても、入れなさすぎても良くない」 という考え方を持つことです。
そのうえで、
- 簡易式でおおまかな目安を出す
- 必要に応じて予測式で精度を上げる
- 状態をみながら柔軟に調整
この流れを意識すれば、臨床での栄養管理に自信を持てるようになりますよ💡