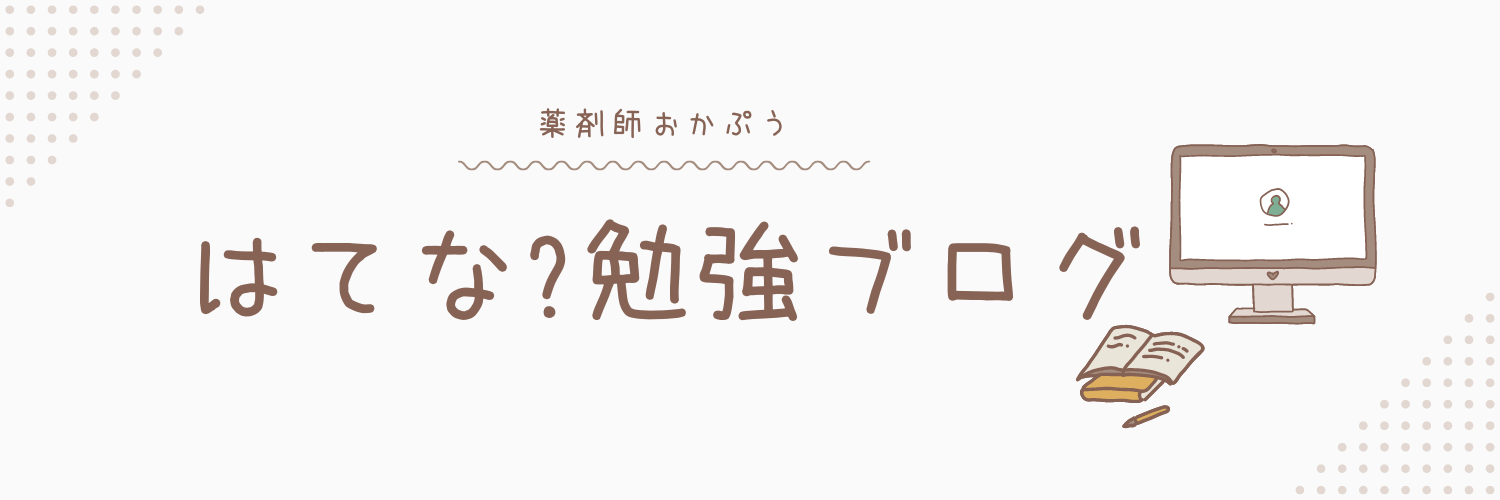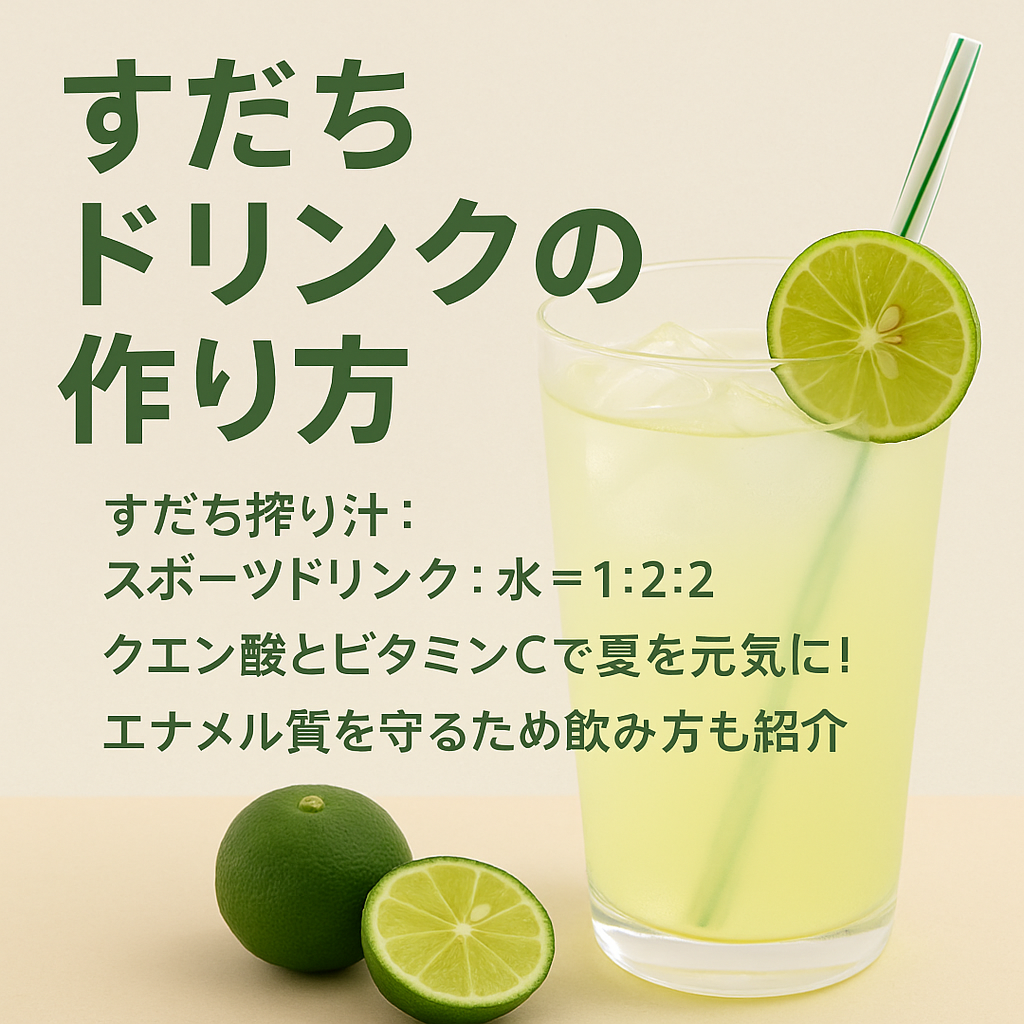はじめに
栄養補助食品は、病院や在宅医療の現場でよく使われる「少量高カロリー設計」の製品です。1パックで200kcal前後を効率的に補給できる点は魅力的ですが、実際に患者さんからは「味が合わなくて続けられない」という声も少なくありません。
僕自身も近所のドラッグストアで、同じ容量・同じ200kcalの商品をいくつか飲み比べてみました。その結果、数十円安い商品は明らかに風味が劣り、「これを毎日続けるのは正直厳しい」と感じました。栄養補助食品は「飲めるかどうか」で効果が左右される、ということを改めて実感しました。
味覚の好みとフレーバーの重要性
患者さんの嗜好や摂取状況は多様です。
- 甘味嗜好のある方:バニラ・ストロベリー・コーヒーなどの甘いフレーバーを受け入れやすい
- 甘味が苦手な方:コーンスープ・ポタージュ・コンソメなどの塩味系が適する
- 治療による味覚変化:抗がん剤治療中などは、金属味や過敏な味覚変化で普段好んでいた味を避けるケースも多い
しかし実際のラインナップは甘いフレーバーが中心であり、塩味系の選択肢は限られているのが現状です。多様なフレーバーを揃えることは、患者アドヒアランスの向上に直結します。
栄養設計の特徴と課題
栄養補助食品の多くは、**低容量(125mL程度)で高カロリー(200kcal前後)**を実現するため、脂質比率が高い設計になっています。
- 一般的に100mLあたり160kcal超 → 脂質からのエネルギー比率が40%以上となる製品も多い
- 糖質主体の商品や、たんぱく質強化型の商品もあるが、摂取目的に応じて選択が必要
栄養管理の視点では、**PFCバランスや窒素/非たんぱくカロリー比(NPC/N比)**も意識する必要があります。特に高齢者や低栄養状態の患者さんに対しては、単にカロリー補給だけでなく、筋肉維持や代謝効率を考慮した設計が求められます。
現場での工夫
臨床現場では以下のような工夫がよく行われています。
- 複数のフレーバーを提示し、患者自身に選択してもらう
- 冷却してデザート感覚にしたり、温めてスープ風にするなど、温度による味覚変化を利用
- 食事や料理に混ぜ込み、直接「飲む」以外の形で提供
こうした小さな工夫が、摂取継続率を大きく左右します。
まとめ
栄養補助食品は「エネルギー効率」や「価格」だけでなく、味の受容性と継続可能性が極めて重要です。実際に飲み比べをしてみると、わずかな風味の差が「続けられるかどうか」を決定づけることがよくわかります。
患者さんやご家族が選ぶ際は、可能であれば複数のフレーバーを試して、自分に合ったものを見つけることをおすすめします。医療者の立場からも「価格より継続性」を重視し、患者さんが長期的に取り組める栄養補給法をサポートしていくことが大切だと感じています。