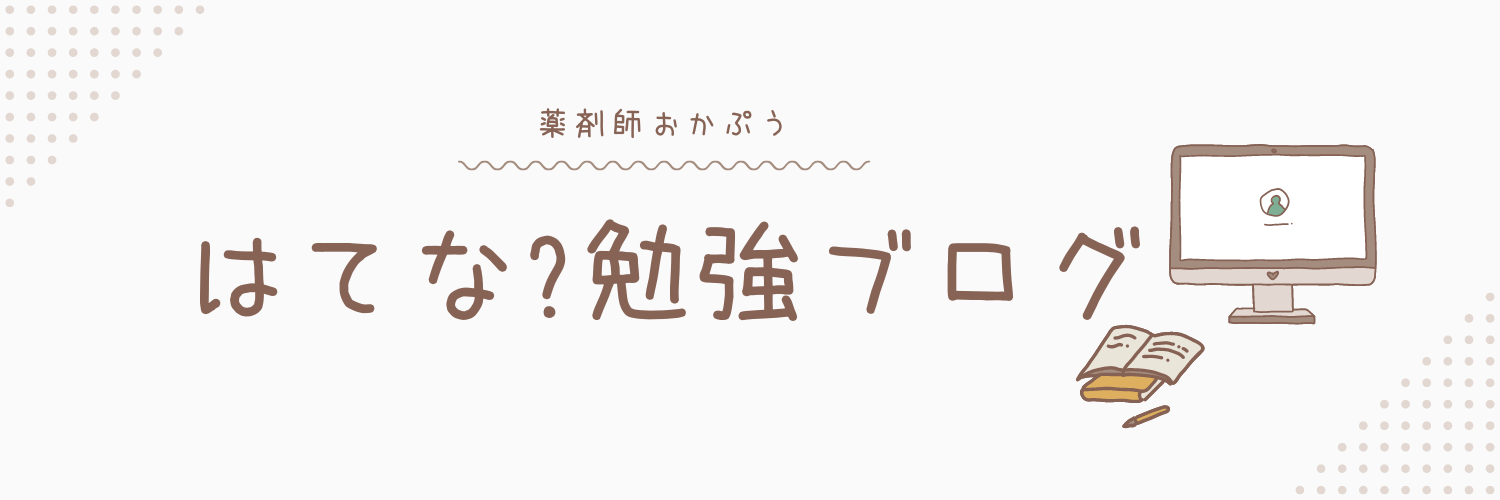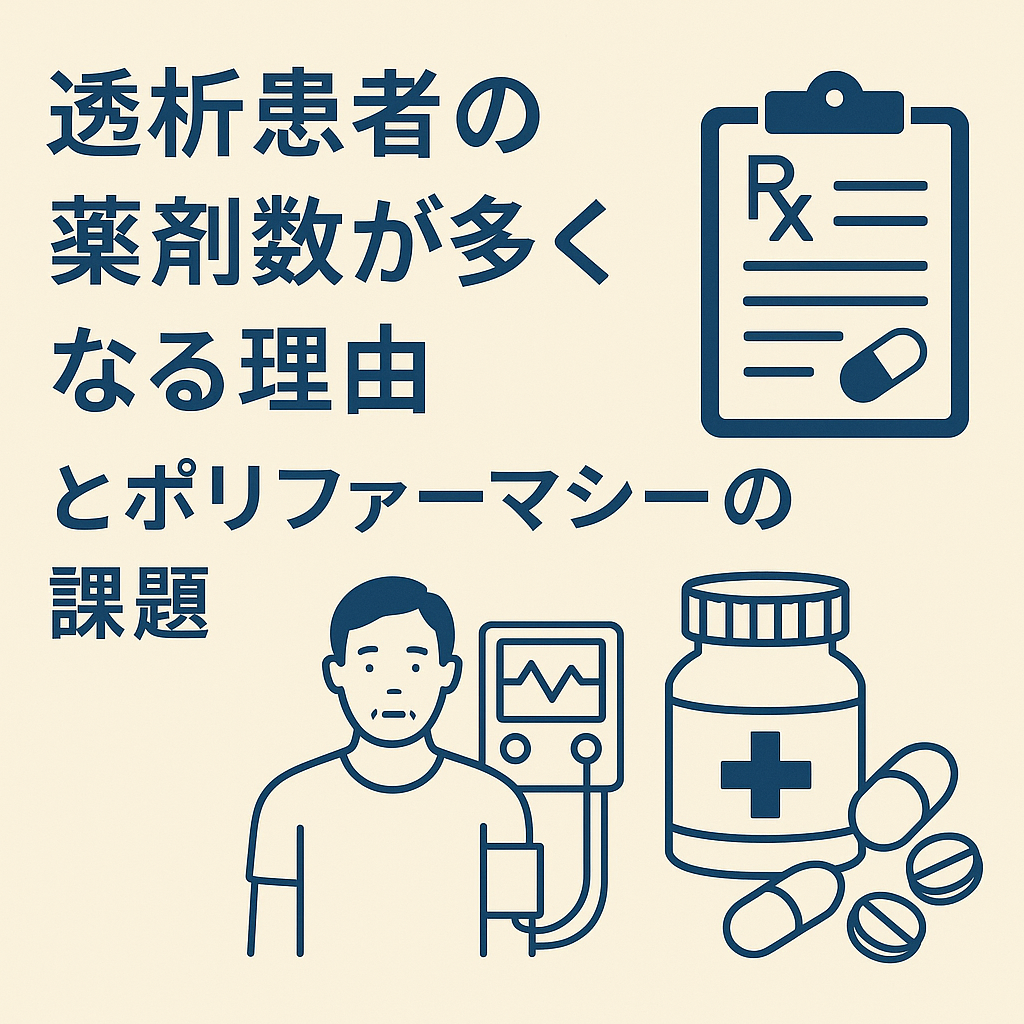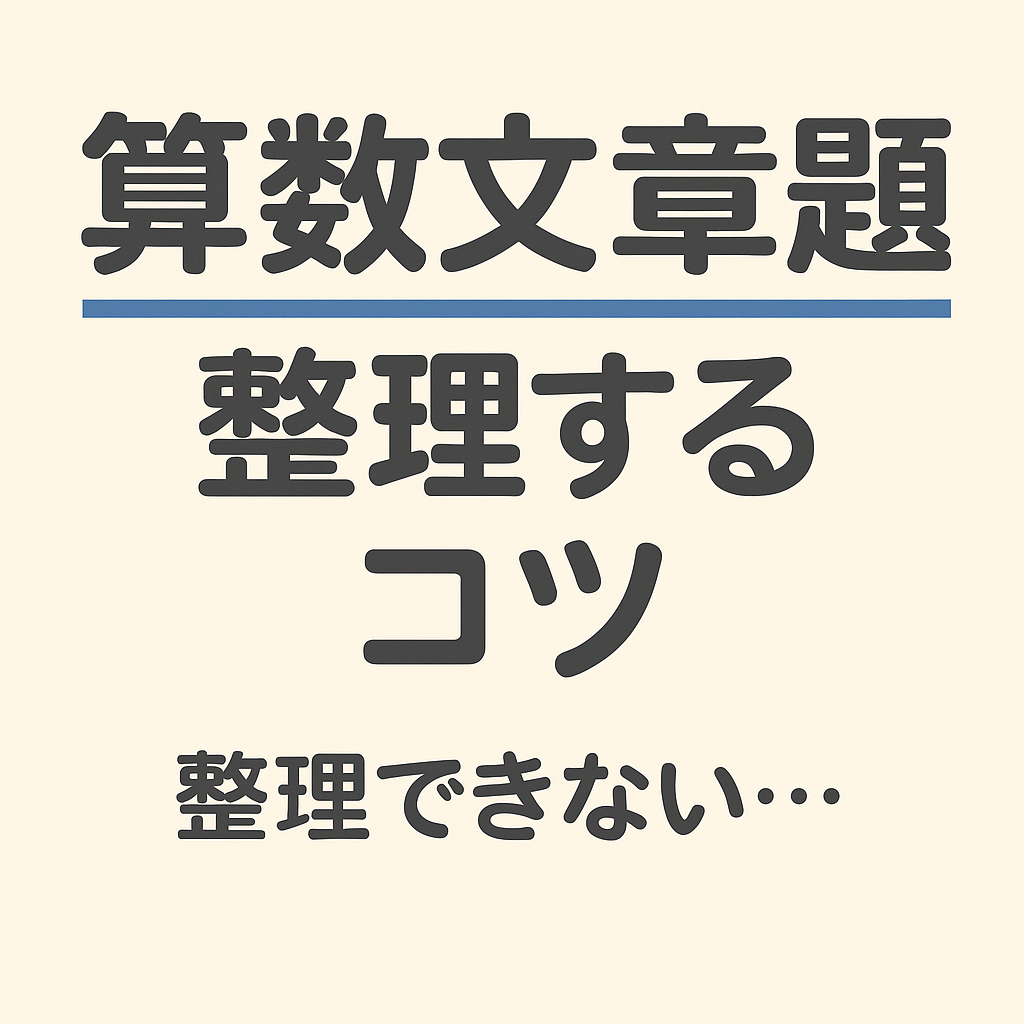透析患者さんを日常的にみていると、ほとんどの方が多剤併用になっているのを実感します。実際、10種類以上の内服をされているケースも珍しくなく、薬剤師として「本当にこれだけ必要なのか?」と考えさせられる場面は少なくありません。
では、なぜ透析患者さんはこれほど薬が増えるのでしょうか。
薬剤数が増える主な要因
① 腎機能を薬で代替する必要がある
腎臓は老廃物排泄や電解質調整、ホルモン産生(エリスロポエチン・ビタミンD活性化など)を担っています。
透析になるとこれらの機能が失われるため、薬で補うことになります。
- 貧血治療薬(ESA・鉄剤)
- 骨ミネラル代謝改善薬(活性型ビタミンD、カルシウム受容体作動薬など)
- リン吸着薬、高カリウム血症対策薬
② 透析による薬・栄養素の除去
透析では尿毒素とともに、水溶性ビタミンや一部薬剤も除去されるため、ビタミン製剤や補充療法が必要になります。
③ 原疾患・合併症の治療
透析導入の背景は糖尿病・高血圧・動脈硬化などが多く、既往治療薬が継続されます。
- 降圧薬の多剤併用
- 糖尿病治療薬(インスリン含む)
- 脂質異常症治療薬
④ 透析特有の症状コントロール
- かゆみ(抗ヒスタミン薬)
- 不眠(睡眠薬)
- 透析中の血圧変動(昇圧薬)
- 慢性疼痛(鎮痛薬)
こうした透析生活特有の症状対策で、さらに処方が追加されます。
ポリファーマシーの視点
薬剤数が増える背景には臨床的な必然性がある一方で、
- 複数薬効の重複
- 長期間漫然と継続される処方
- 服薬アドヒアランスの低下
といった問題も同時に存在します。
特に透析患者さんは、高齢者であることが多く、認知機能や身体機能の低下も重なりやすいため、ポリファーマシーによる有害事象のリスクはさらに高まります。
まとめ
透析患者さんの薬剤数が多くなるのは、腎臓機能を薬で補う必然性に加え、透析の影響や合併症治療、生活の質を保つための薬が重なるためです。
ただし、その裏側にはポリファーマシーの問題があり、「必要な薬」と「再評価すべき薬」を見極める視点が常に求められています。