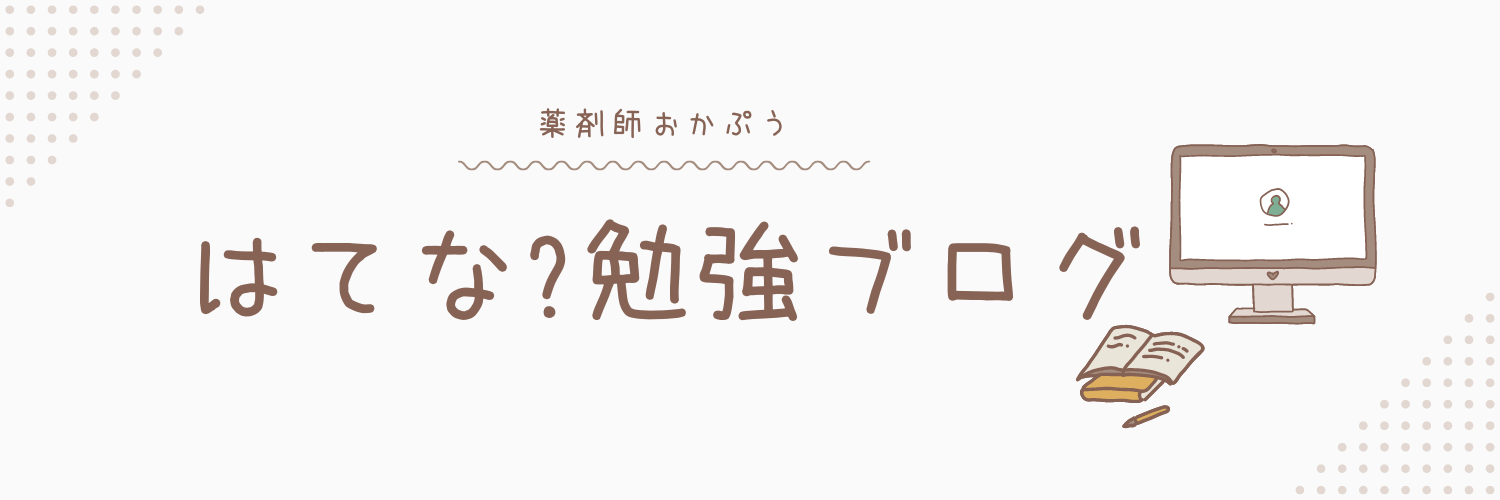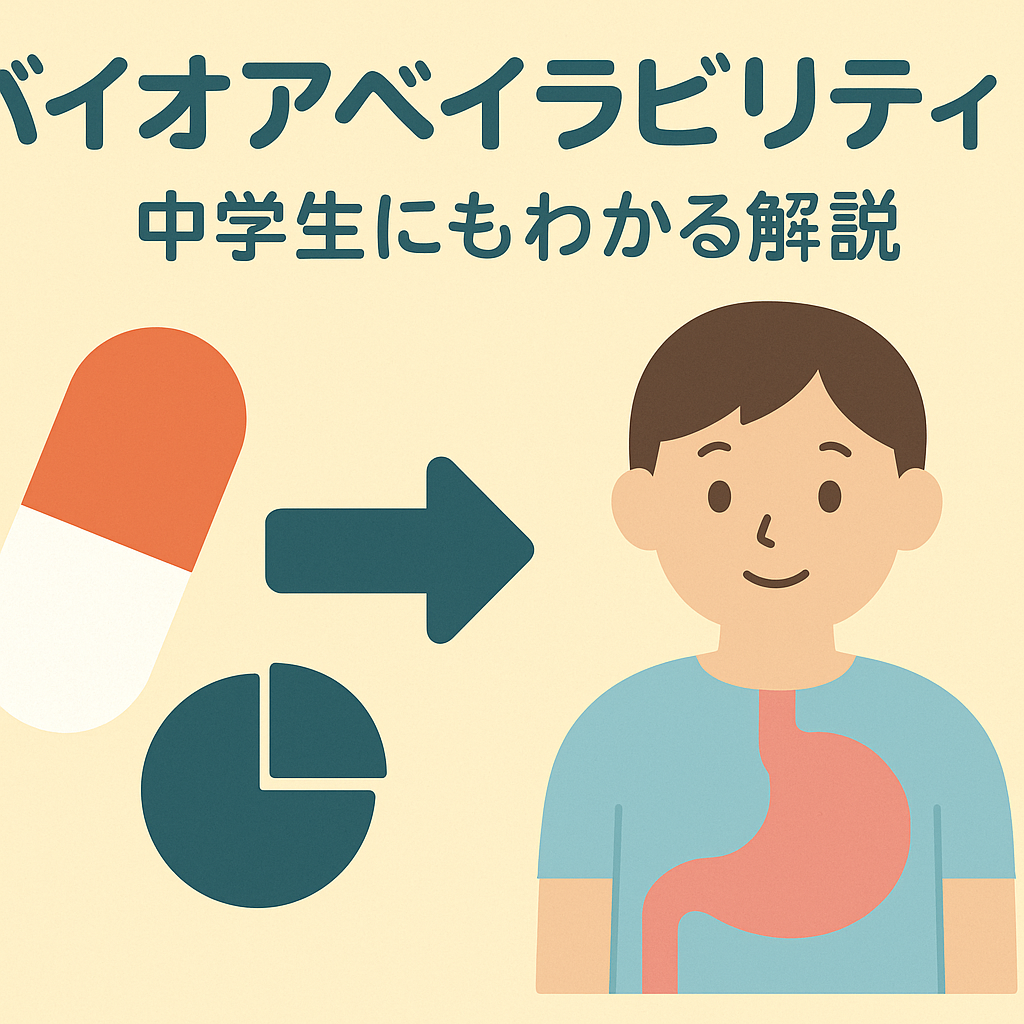●薬の「タンパク結合率」ってなに?
私たちが薬を飲むと、薬は血液の中を流れていきます。
血液の中には「アルブミン」っていうタンパク質があって、薬の中にはこのアルブミンにくっつくものがあります。
この「くっつく割合(%)」のことをタンパク結合率って言います。
たとえば、
- 100ある薬のうち、90がアルブミンにくっついている → タンパク結合率90%
- 逆に、10しかくっつかない → タンパク結合率10%
という感じ。
で、大事なのは、**アルブミンにくっついている薬は「おとなしくしてて、あまり働かない」**ってこと。
逆に、**くっついてない薬は「自由に動いて、体に効いてくる」**んだよ。
●アルブミンが少ないとどうなるの?
アルブミンが少ない(=低アルブミン血症)と、薬があまりくっつけなくなっちゃう。
つまり、「自由に動く薬」が増えてしまうってこと。
それってどうなるかというと…
➡ 同じ量の薬でも、効きすぎたり、副作用が出やすくなったりすることがあるんだ。
とくに、タンパク結合率が高い薬(たくさんアルブミンにくっつくタイプの薬)は注意が必要。
●まとめ
- 薬は血液の中のアルブミンとくっつくことがある。
- くっついている薬は働かない。くっついてない薬が体に効く。
- アルブミンが少ないと、「効く薬」が増えすぎて、効きすぎたり副作用が出たりすることがある。